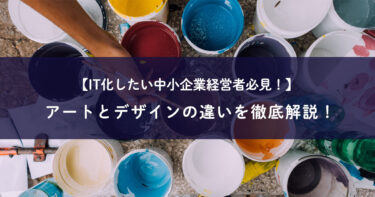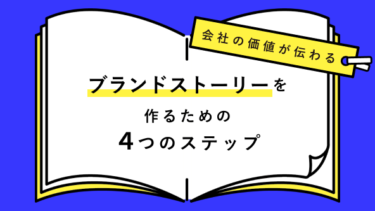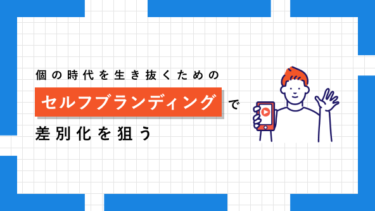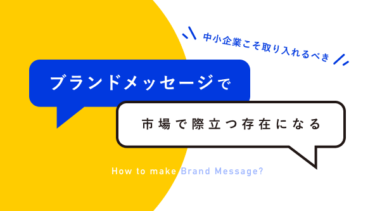今回は、「伝統企業のブランド戦略」について、「湖池屋」のリブランディングの事例をもとに徹底解説していきます!
伝統のある企業ではあるけれど、市場として今後の展開が危うく、既存の顧客・技術・見せ方だけではやっていけない。
そう考えている方にピッタリな記事になっているので是非見ていってください!
- 湖池屋のブランド戦略
- 湖池屋のブランド戦略の活用方法
また、事例の前に、まずは「ブランディング」とか「リブランディング」とか教えてくれよ、という方もいらっしゃると思いますが、今回はあえて事例から紹介していきます。
というのも、「ブランディング」や「リブランディング」について説明しようとすると、内容がどうしても抽象的になってしまいます。
ですので、「湖池屋」の例をもとになんとなくでも「ブランディングってこういうものなのか!」と言ったイメージを持ってもらいと思って、あえて、「事例」から説明していきます!
そもそも「ブランディングとは?」など、言葉の定義から知りたい方はこちらがおすすめ!
さらに、この記事の最後には、それらを踏まえて、「では、自社にどう活かすのか?」というところまで書き込んでいます。
ただ読んで終わるだけではなく、「自社だったらどうするか?」を考えながら読んでもらえると、より内容が入っていくと思います。
ぼんやりとでも「ここはうちに当てはまるな」「これだったらうちでもできそうだな」と考えながら読んでみてください!
湖池屋ってどんなお店?業界の現状は?

湖池屋は、1953年に小池和夫氏が創業し、2021年に創業68年になるお菓子メーカーです。
創業後、1962年に創業者の小池和夫氏がポテトチップスののり塩味を発明し、1967年に日本で初めてポテトチップスの量産化に成功しました。
現在では、だれもが知るヒット商品の原点となる商品を生み出したお菓子メーカーですが、実は、市場の変化や消費者動向の変化によって、決して今後も安泰という状況ではありませんでした。
湖池屋がどんな問題をどのように解決していったのか、次の章で詳しくお話ししていきます。
湖池屋がブランド戦略を始めるまで
湖池屋は、商品を売り出していく中で、次の問題に直面します。
- 平均価格の下落、市場減少
- 価格の固定化
- 顧客の商品に対するイメージの固定化
平均価格の下落と市場減少
まず、菓子の業界全体で言えば、市場規模2兆円近くあり、中でもスナック菓子は市場規模約3000億円と言われ、チョコレートに次ぐ市場規模で、決して市場規模が小さいというわけではありません。
しかし、ポテトチップスに関して言えば、近年は平均売価が下落しており、それに伴い市場減少しているという状況です。
この状況に至ったのは、まさに消費者の考え方・価値観の変化が主な原因と言えます。
消費者の考え方・価値観の変化を一言で言うと、
「量→質へ」
これにつきます。
価格の固定化とイメージの固定化
近年の日本では、人口は減少しているものの世帯数は増加しているため、利便性やこだわり(独自の特徴)を持った商品が求められるようになりました。
その市場の変化に適応していったのが、チョコレートやアイスの市場と言えるでしょう。
チョコレートやアイスの市場では、プレミアムなどの付加価値をつけることで、量では劣るものの、原材料やパッケージ、メッセージ性にこだわり、顧客に特別感を持たせることで差別化し、価格競争から離れたと言えるでしょう。
一方で、ポテトチップスの市場では主力商品であるのり塩味やコンソメ味が一般化(価格の固定化・顧客の商品に対するイメージの固定化)されたことで、市場が停滞している現状です。
同じお菓子業界でも、プレミアムなどの付加価値をつけることで商品の差別化を図ってきたチョコレートやアイスと日々の価格競争に怯えるポテトチップスでは、将来性に大きな違いがありました。
湖池屋では、独自にユーザーにアンケートをとり、スナック菓子を選ぶときの消費者の基準を調査し、以下のような項目がスナック菓子を購入時に重要視されていることを確認しました。
- 食べ切れる量・サイズであること
- 国産原料など拘った材料が使われていること
湖池屋は、これらの業界の現状や、データを基にブランド戦略に乗り出しました。
湖池屋はどのようにリブランディングしたのか?
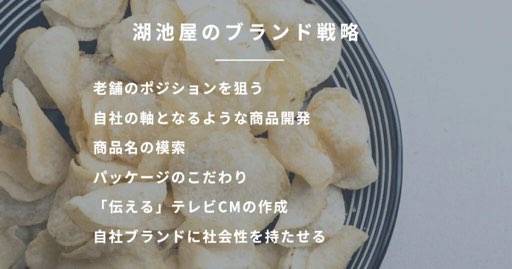
では早速、湖池屋のブランド戦略、リブランディングはどんなものであったのかを詳しく解説していきます。
老舗のポジションを狙う
湖池屋では、「ポテトチップスの老舗」と言う企業ポジションを目指すことで、企業のブランディングの再確立を目指しました。
それにあたり、経営トップが先頭に立ち、次のような変革を実施しました。
- コーポレートロゴの変更
- 全社員にブランドブックの配布
- スローガンの設定
①コーポレートロゴの変更
楕円での形でおなじみであったロゴから、老舗として連想されるように家の紋をイメージした、六角形の中心に「湖」を文字化したハウスマークに変更しました。
よし、アイコンはこれだ!!
ええ、言いたいことはわかります。わかりますよ。しかし!新生・湖池屋のロゴは「六角形」なのです。親しみ・安心・楽しさ・本格・健康・社会貢献の意味があるのです(*´ω`*)今後もよろしくお願いします! pic.twitter.com/qwk2J7d0bV
— 湖池屋 コイケヤ【公式】 (@koikeya_cp) June 16, 2017
「老舗」のイメージを連想させると同時に、六角形には、これまでの核となるような価値であった「親しみ」「安心」「楽しさ」に加えて、「本格」「健康」「社会貢献」を加えた、六つの価値を表現しています。
②社内のブランディング
湖池屋は社内向けのブランディング、インナーブランディングも行いました。
- 企業の考えやルールをまとめたブランドブックを社内に配布
- 社屋を一新
まず、新たな湖池屋を作るにあたって、インナーブランディング施策として、企業の考えやルールをまとめたブランドブックを制作して、全社員に向けて、配布しました。
さらに、社屋も一新し、「老舗」のイメージを連想させるような玄関や門構えに変更することで、「湖池屋にはポテトチップスを作る料理人がいる」と言うイメージを社内に根付かせました。
こういった施策を行うことで、社員たちが持つイメージを一新し、そこからお客様にも伝染させていくことを目指しました。
このように社外に対してだけではなく、社内のブランディングも同時に行ったことは特徴的と言えるでしょう。
③スローガンの設定
湖池屋では、「ポテトチップスの老舗」というブランドを再確立していく上で、「イケイケGOGO!」というスローガンを設定しました。
このスローガンは、湖池屋の1970年代のテレビCMから着想を得ています。
「イケイケGOGO!」という勢いのあるフレーズであることや、パイオニア精神やチャレンジ精神を煽るようなスローガンとして採用しました。
このスローガンには社員が仕事をする上での共通認識として次の3つ意味が込められています。
- 「環境や社会の変化に順応して、新たな食生活の創造を」
- 「新しい方へ、イケイケ!」
- 「面白い方に、イケイケ!」
変革はスローガンやコーポレートマークや社屋にとどまりませんでした。
社章や名刺、紙袋、封筒に至るまで行われました。
紙袋においても国産紙を使用するという徹底ぶりで、細部までこだわることが社内の変化につながっていくと考えました。
まず認識・意識を変えることで、見た目が変わり、生活が変わってきて、行動が変わっていくという流れを意識しています。
自社の軸となるような商品開発
湖池屋のポテトチップスは、日本で初めて大量生産されたポテトチップスでしたが、現在では「他社との差がなくなっており、商品が価格で選ばれるようになった」ことが問題となっていました。
その問題を解決する、キーマンとなったのは、元キリンビバレッジの社長で「FIRE」や「生茶」を生み出した伝説のマーケター、佐藤氏でした。
佐藤氏は湖池屋の新たなブランディングの際に「一品で会社を変える」をコンセプトとして挙げました。
失いかけたホコリ・プライドが新たに生まれれば会社が復活すると考えて生まれたのが「KOIKEYA PRIDE POTATO」でした。

この商品を制作する際に、以下の3つが意識されていました。
- 「ライバルを見ないこと」
- 「考えるべきは会社自身のルーツ、お客様のこと」
- 「業界で最高に美味しいポテトチップスを作ること」
「ライバルを見ないこと」に疑問を覚える方もいるかもしれません。
しかし、佐藤氏は会社自身のルーツや顧客を第一に考えており、とにかく業界で最高に美味しいポテトチップスを作ることを重要視しました。
そして、「KOIKEYA PRIDE POTATO」が生まれました。
「KOIKEYA PRIDE POTATO」には次のような特徴があります。
- 100%国産のじゃがいもを原料にしたこと
- じゃがいもの良さ、味わいが伝わるような揚げ方・製法に拘ったこと
- 従来の暖色系で視認性の高い赤や黄色を用いたパッケージではなく、「真っ白の」スタイリッシュな色で、これまでにない縦に立つ新しい包装を採用
このように「ライバルがどうか」ということはなく、とにかく「最高のポテトチップス」を目指しました。
その結果、発売後すぐに、SNSで話題になり、様々な顧客層に購入されることに至りました。
売り上げは年間20億を売り上げれば大ヒットと言われる中で、40億円を売り上げる大ヒットとなりました。
商品名の模索
湖池屋の社長である佐藤氏は、「湖池屋の妥協なく一番美味しいプレミアムなポテトチップスを象徴するものとして出す」ことを掲げました。
しかし、あまりにも「老舗の本気!」と言う気持ちが前面に出過ぎてしまうと、消費者とのイメージとミスマッチが起きてしまいます。
そのため、様々な商品名の案を比較検討した上で、本気であると言う気持ちを前面に出すのではなく、チャーミングで愛される商品になることと会社のプライド、どちらの要素も持ち合わせた商品名「KOIKEYA PRIDE POTATO」に決定しました。
パッケージのこだわり
最高のポテトチップスが完成したとは言え、それを包むパッケージが従来の物と変わらなければ、消費者のイメージは、相変わらず、「いつもの普通のポテトチップス」になってしまいます。
そこで、湖池屋はパッケージのデザインにもこだわりました。
- 訴求したい情報以外を削ぎ落とす
- パッケージのデザインを白基調に
- シンプルなデザイン

湖池屋では、当初、このパッケージのデザインを考えた時に、製法や材料など、商品情報をキャッチーなものにまとめて、とにかく多くのものを載せようとしていました。
しかし、それでは、何を本当に訴求したいのかが不明確になってしまいます。
伝えたいことが何か不鮮明になってしまうことを防ぐために、訴求したい情報以外を削ぎ落とし、パッケージのデザインも白を基調とし、そこにポテトチップスが「一枚一枚」綺麗に並べられたシンプルなデザインにすることで他の商品と差別化することに成功しました。
「伝える」テレビCMの作成
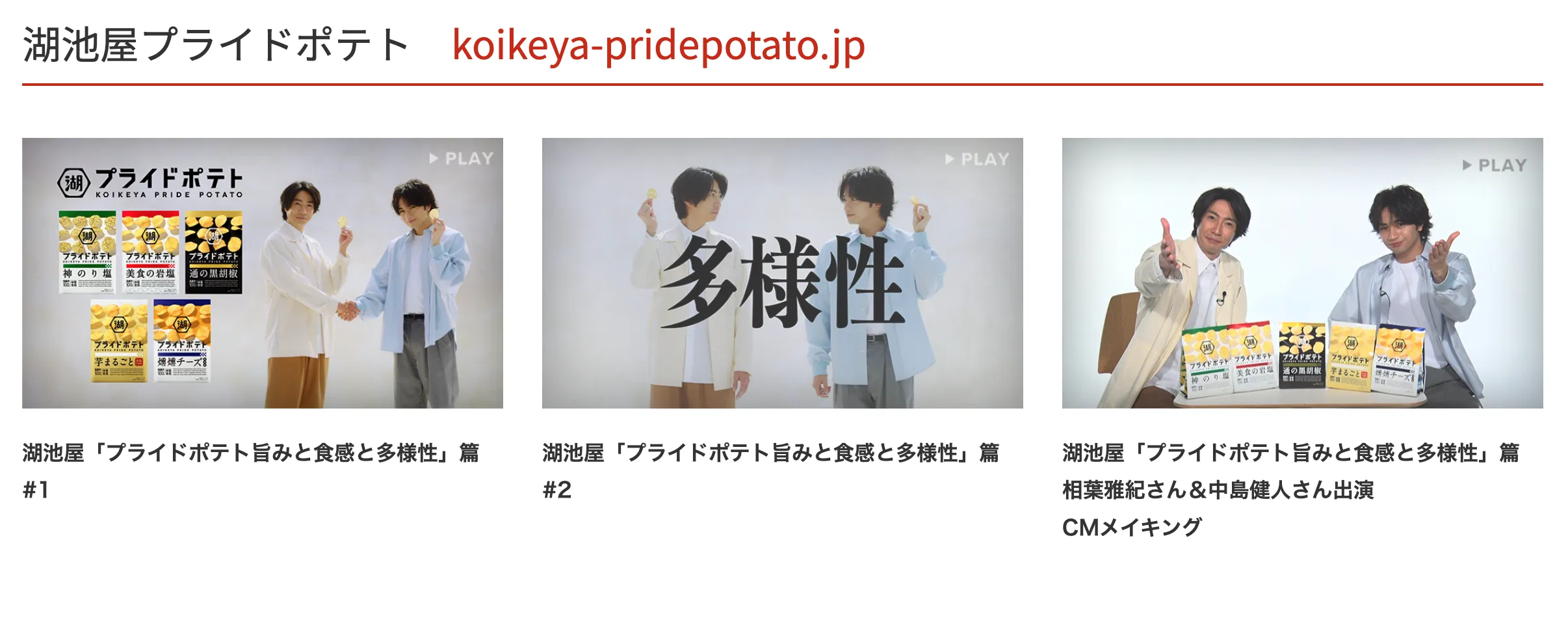
自信のある商品を開発できたことから、テレビCM制作時には、「とにかく印象の残るCMを」ということが意識されていきました。
その考えから古典的ではあるものの壮大な曲に単純な歌詞、異様に目立つテレビCMが制作されました。
結果として、CMがテレビにオンエアされると、「なんだ今のCMは?」とSNSで反響を呼び、多くの人にシェアされるCMになりました。
反響のきっかけになればと考えられた、「あえて商品の名前を言わない」CMも制作し、この反響を後押ししました。
自社ブランドに社会性を持たせる

湖池屋は、『JAPAN PRIDE POTATO』を開発した上で、ブランドに社会性を持たせる取り組みも行っています。
その取り組みの一つとして、世界文化遺産の神が宿る島と言われる宗像・沖ノ鳥との協力がが挙げられます。
この取り組みでは、「宗像の海を守る」をテーマに、湖池屋が限定フレーバーを開発・販売を行ないました。
この製品には、宗像市で作られた醤油や有明海の海苔、鐘崎漁港の穴子など、地域ならではの食品が使われています。
この製品によって、日本が誇る地域の伝統ある文化や食材を全国各地に広げる、発進していくことができました。
宗像市にとっては、地元のPRになり、湖池屋にとっては、地域貢献をしていると言う社会性を高める結果につながりました。
さらに、この取り組みでは、伝統ある地域ならではの食材をこだわりを持って開発したことで、「老舗」の湖池屋だからこそできたと言う自社のブランディングにもつながりました。
近年、企業にもSDGs(持続可能な開発目標)が求められるようになり、大企業、中小企業問わず、社会問題の解決や環境問題にいかに対応していくのかと言うことが注目されています。
これに対し、湖池屋は、宗像市の活性化と同時に、自社のブランドイメージの向上にも繋げました。
このように、企業がSDGs(持続可能な開発目標)などに取り組む際に、重要なのは、「ただのボランティアでは終わらせないこと」です。
その取り組みによって自社にどのような影響を与えるのかを考慮した上で、実際に行動につなげることが必要不可欠です。
リブランディングとは?

ここまで、湖池屋の事例をもとに、リブランディングがどういうものなのかについて説明していきましたが、そもそも「リブランディング」とは何なのかについて、説明していきます。
リブランディングというのは、
という構図になっていて、直訳すると「再びブランディングする」ことです。
リブランディングは次のような時に行われます。
- 「ブランドイメージ」が作られてしまっているとき
- 明確なブランドイメージはあるものの、時代や事業環境の変化に合わせてブランドイメージを変化させたい時
- 何となく事業は走らせているものの、意図しない「何となくのブランドイメージ」が作られてしまっている時
手法としては、主に二つに分類されます。
- コンセプトから再設計するリブランディング
- クリエイティブ(ロゴやパッケージ)だけを見直すリブランディング
①はまさに、記事で紹介した湖池屋のブランド戦略が当てはまります。
一方で、②については、ブランドのコンセプトを変える必要はないため、WEBサイトや、パッケージを変更する際も、コンセプトやブランドイメージと相違がないか確認しながら設計する必要があります。
なぜブランディングは大事なのかが丸わかり!資料ダウンロードはこちら
湖池屋のブランド戦略をどう自社に活かすのか?

ここまで、湖池屋のブランド戦略からリブランディングの定義までを解説してきましたが、この記事を読んで多くの人が「結局、自社にどう応用すればいいのか?」というのが、いちばんの問題となるでしょう。
ここからは、ブランド戦略で重要なことや、湖池屋のブランド戦略を自社に活かすためのステップを解説していきます。
湖池屋のブランド戦略を活かすために重要なこと
湖池屋のブランド戦略を活用する際に大事なのは、「ブランド戦略」という言葉で、問題を一括りにしないことです。
一言に「ブランド戦略」と言っても、企業が抱える問題は、十人十色です。
例えば、リブランディングの種類を紹介したことにも重なりますが、
「自社のコンセプトを再設計するのか、否か?」
この時点で、企業が取るべき施策というのは異なります。
しかし、どの企業にも言えることは、行うべき施策というのは、「社内に向けたものなのか、社外に向けたものなのか」のどちらかであるということが言えます。
本記事で紹介した、湖池屋の事例で言えば、次のように分けられます。
- 社屋の一新
- 社員への、自社のブランドに関する資料の配布
- ロゴの刷新
- 新商品・パッケージの開発
という風に分けられます。
どちらにも共通しているのは、社員にしろ、消費者にしろ、同じ一貫したブランドイメージを共有していることです。
ブランディングの際に、社員や消費者のどちらか一方だけにブランドイメージを共有するのはあまり得策とは言えません。
湖池屋の例でわかりやすく考えてみましょう。
新商品「KOIKEYA PRIDE POTATO」を開発して、消費者向けのブランドイメージを刷新できたとします。
しかし、もしも、そのブランドイメージに社員の考えが追随しておらず、自分達の事業に自信が持てなければ、その商品を販売する時やCMなどで広める時にチグハグな広告、セールスになるでしょう。
これは、ブランドイメージが全員に共有できていないと、新しいブランドイメージではなく、従来のブランドイメージが邪魔をしてしまうためです。
そのため、ブランディングを行う際には、社外に向けた物と社内に向けたものの両方に取り組む必要があるのです。
ブランド戦略のステップ
STEP2. 自社の価値観・困っていることの把握
STEP3. それが今の「ロゴ、営業資料」「社内の雰囲気に反映できているかを確認
STEP4. 反映できていないのなら、どれを改善すべきかを考え、実行する
まず、自社でどのような課題があって、どのような長所があるのかということを把握した上で、社内・社外に分けてどのような施策を打つのが最適か考えましょう。
「ブランド戦略」と一言にまとめてしまうと、すごく難しいことに考えられますが、「社内で困っていること・共有したい価値観」、「社外で困っていること・共有したい価値観」と分けてそれぞれ考えれば、自ずと何をすべきなのか見えるでしょう。
まとめ
ここまで、湖池屋のリブランディングの事例をもとに、ブランド戦略について解説してきました。
ブランド戦略では、課題や長所を把握してから、社内と社外に分けて施策を打っていくことが重要になります。
ぜひ湖池屋の事例を参考にしてリブランディングを行ってみてください!