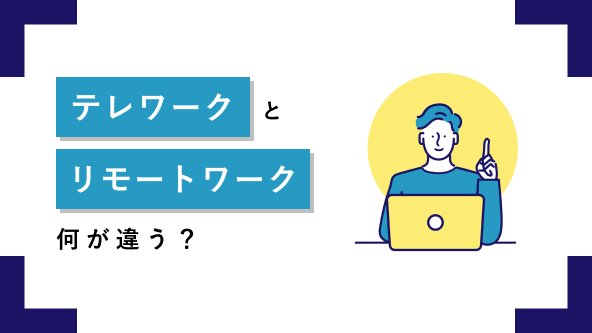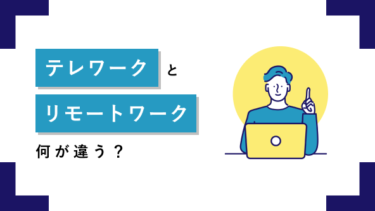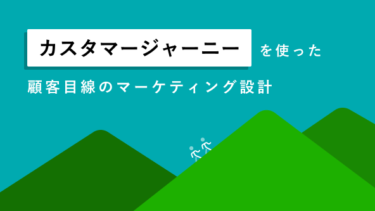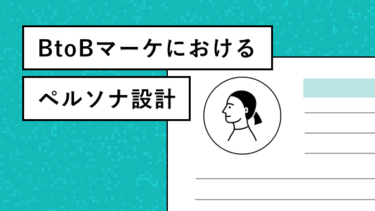新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業で導入が進められている「テレワーク」「リモートワーク」という言葉が、頻繁に出てくるようになりました。
テレワークとリモートワークは同じような意味で使われ、ともに出勤せずに働くという意味ですが、違いはあるのでしょうか。
ここでは、混同しやすい「テレワーク」と「リモートワーク」の違いを説明すると共に、その導入事例、またテレワーク導入のメリット・デメリットについてご紹介します。
テレワーク・リモートワークとは

テレワークとは?
テレワークとは、従業員がオフィスや会社の場所に集まることなく、離れた場所から仕事を行う働き方のことです。厚生労働省ではテレワークとは「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義しています。
テレワークとは | テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)
テレワークは場所という観点からさまざまな働き方があります。どのような働き方があるか見ていきます。
ー在宅勤務
在宅勤務は、従業員が自宅や他の場所で仕事を行う働き方のことです。
オンラインコミュニケーションやテクノロジーを活用し、通勤やオフィスに集まる必要がなくなります。時間と場所に制約されずに業務を遂行することができ、柔軟性や効率性の向上をもたらします。
しかし、適切なコミュニケーションやタスク管理が重要であり、自己管理能力やモチベーションの維持が求められます。
ーサテライトオフィス勤務
サテライトオフィス勤務とは、企業の本拠地以外に設けられた小規模オフィスで働くことです。
サテライトオフィスは主に地方や他の都市に設けられ、従業員がより身近な場所で働くことができます。これにより、通勤時間の削減や地域における雇用創出が可能となります。
サテライトオフィスでは、主要な業務機能をサポートし、必要な場合には本拠地と連携します。従業員にとっては柔軟性や効率性の向上をもたらし、地域社会への貢献も期待されます。
ーモバイル勤務
モバイル勤務とは、携帯電話やノートパソコン、タブレットなどのモバイルデバイスを利用して、場所にとらわれずに仕事を行う働き方のことです。
従業員はオフィスに固定されず、自宅やカフェ、出張先などで業務を遂行します。インターネット接続があれば、コミュニケーションやタスクの管理、ファイルの共有などをリアルタイムで行うことができます。
モバイル勤務は柔軟性と自由度を提供し、効率的な働き方を実現しますが、適切な時間管理や作業環境の確保が重要です。
リモートワークとは?
続いては「テレワーク」と同じ意味合いで使われることが多い、「リモートワーク」について解説していきます。
一般的にリモートワークとは、完全にオフィス以外の場所から働く形態をいいます。
例えば、オフィスに自分のデスクがなく、会社から支給されたノートパソコンを活用して家で働くスタイルはリモートワークとなります。
基本的に、テレワークのように通勤を伴わないため、リモートワーカーは会社のオフィスからは地理的に遠い場所に住んでいるケースがほとんどです。
テレワーク・リモートワークの違い

テレワークとリモートワークには、「オフィス以外の場所で働く」という意味が共通としてありますが、具体的な違いはあるのでしょうか。
国や自治体では主にテレワークが使われますが、世間一般では両者を同じ意味で認識しているため、「テレワーク=リモートワーク」で問題はないでしょう。
テレワーク・リモートワークが広まった背景

今後も増えていくと予想されているテレワーク・リモートワークですが、なぜ、中小企業・大企業に関わらず、今まで日本にはなかった新しい働き方に注目が集まっているのかを考えていこうと思います。
背景①|労働人口の減少によるもの
テレワーク・リモートワークの導入を検討する企業が増えてきた大きな社会的背景の一つに、「労働人口減少」の問題があります。
どの中小企業・大企業も口を揃えたように問題視している人材不足の課題。
特に、結婚や妊娠、育児や介護を行う必要に迫られた際、これまでの日本企業は、会社を辞めるか休職するかの選択肢しかありませんでした。
しかし、ITやインターネットなどの技術革新により、「場所にとらわれない働き方」といった選択肢を持つことができるようになりました。
「ちゃんと仕事をしてくれるなら、働く場所は問わない」と考える経営者が増えてきたことも、テレワーク・リモートワークの導入が進んでいる要因の一つだと考えられます。
背景②|コスト削減のため
オフィス業務には大きなコストが発生します。
◉オフィス業務にかかる主なコスト
- オフィスの家賃
- オフィスを飾るための什器・備品類
- 水道光熱費、通信費
- 従業員に支給する交通費
などなど、さまざまな費用が経費として必要です。
テレワークを実現することによってオフィススペースの縮小化や、備品、水道光熱費、通信費なども削減できます。また、そもそも出社が必要なくなるので交通費の削減にもつながります。
これらの費用を削減することにより、余った経費を事業発展のために活用できます。
背景③|インターネットなど情報通信を行えるインフラが整ってきたから
インターネットなど情報通信を行えるインフラが国全体で整ってきたことも、テレワーク・リモートワーク普及の背景として考えられます。
例:ZOOMなどの高性能・低価格なWeb会議システムの普及
テレワーク・リモートワークにおいて、情報通信技術の発達は必要不可欠です。
そして、これらのツールをいかに使いこなすことができるかが、テレワーク・リモートワークの推進が上手くいくかどうかの分かれ道になるのではないでしょうか。
企業のテレワーク・リモートワーク導入ポイント

テレワークやリモートワークは、企業・従業員にさまざまなメリットがあります。
一方で導入後の問題も考えられます。
導入のメリットとは?
まずはメリットについて考えていきます。企業がテレワーク・リモートワークを実施すると以下のようなメリットが期待できます。
- 生産性の向上
- 新たな人材の確保につながる
- 企業ブランディングでイメージアップ
- 事業継続計画(BCP)の支えになる
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
メリット1|生産性の向上
総務省の調査によれば、テレワークを導入した企業の50.1%が「労働生産性の向上」をテレワークの導入目的として挙げています。
また導入した企業の実に82.1%が「労働生産性向上に効果がある」という回答をしており、多くの企業で生産性向上の実績があることが分かります。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd144320.html
メリット2|新たな人材の確保につながる
テレワークにより通勤の問題を減らすことができるため、地理的に就労が困難だった優秀な人材の確保が可能となります。
また子育てや介護のために働けなかった人々もテレワークにより、会社を辞めることなく続けてもらうことが可能となります。
このように人材確保の幅が広がり、優秀な人材を獲得することが実現します。
メリット3|企業ブランディングでイメージアップ
企業ブランディングを強化し、積極的に働きやすい環境づくりを行っていることが世間に伝われば、好感度アップにつながります。
テレワークにより従業員のワークライフバランスを考慮した就労ができる環境を整えることで、企業の人気度も向上し、採用においても他社競合との差別化が図れます。
関連記事
メリット4|事業継続計画(BCP)の支えになる
BCP(Business Continuity Planning、事業継続計画)とは、災害や感染症の拡大などの緊急事態が発生したときに、企業の損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のことです。
突然の災害や感染症の拡大が起こっても、事業を継続できるようにテレワークを導入しておくことは大切です。
非常時には通勤しなくてもオフィス以外の自宅やサテライトオフィスなどで勤務できる体制をとっておけば、問題なく事業継続が可能になります。
関連記事
導入のデメリットとは?
次はデメリットについて考えていきます。企業がテレワーク・リモートワークを実施すると以下のようなデメリットが考えられます。
- 労災の範囲が曖昧になる危険性がある
- コミュニケーションが希薄になってしまう
- 上司の目がないためサボってしまう
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
デメリット1|労災の範囲が曖昧になる危険性がある
一般的に、従業員が勤務中に起こった災害については、労災保険が給付されます。
テレワークで在宅勤務となっている場合、業務の時間とそうでない時間が混在するため、給付条件を見極めるのが難しくなる可能性があります。
もし労災で対応できるか否か迷った場合は、厚生労働省が公表している「テレワーク導入のための労務管理等Q&A集」を参考にしてみるのも良いかもしれません。
http://www.tw-sodan.jp/dl_pdf/13.pdf
労災に認定されるかどうかは、労働基準監督署の判断に委ねられますので、その都度確認が必要となりそうです。
デメリット2|コミュニケーションが希薄になってしまう
従来のオフィスに出社するスタイルの場合、ちょっとしたことでも同僚や上司とコミュニケーションが図れていましたが、テレワークの場合は、社員同士の接触頻度が少なくなってしまうため、コミュニケーションが希薄になってしまう可能性があります。
zoomなどのWeb会議も、対面でのコミニケーションとは違い、話が他者と被りやすく思ったことを発言しにくかったり、感情の機微が読み取りにくく、無愛想に映ってしまうことも…。
こうした際には、自社やチームに合ったチャットツールなどを活用して、認識の齟齬が起きないような仕組み作りが重要になってきます。
例えば、チャットワークやSlack、ハングアウトなどのツールが挙げられます。
デメリット3|上司の目がないためサボってしまう
エン・ジャパンが実施した「中小企業のテレワーク実態調査」の「テレワーク導入の上で難しかったことは何ですか?」という質問に対して、難しかったことの上位に「テレワーク社員の時間管理」といった回答が多く、多くの企業がこの問題に苦労している様子がうかがえます。
https://www.nice2meet.us/telework-demerit-donyu-point
テレワークはメリットもありますが、「少しぐらいサボってもバレないだろう」という社員が出てきてしまう可能性も秘めています。
サボりは言うまでもなく生産性の低下につながり、テレワークの導入を阻害する大きな要因にもなり得ます。サボり防止対策として最も有効なのは、パソコンへのログイン状況や仕事内容を遠隔で管理できるツールの導入です。
稼働時間だけでなく使用したアプリの時間管理や画面キャプチャができる機能を搭載した管理ツールもあり、サボり防止に一役買っています。
まとめ
今回は、テレワークとリモートワークの違いや、導入にした企業の事例やメリット・デメリットについてご紹介させて頂きました。
テレワークとリモートワークは定義の若干の違いがあるものの、基本的には同じ意味合いと考えて問題ないでしょう。
昨今、企業には従業員のライフスタイルにあった働き方を提供できる環境が求められています。
そうした背景の中でリモートワーク・テレワークは重要な役割を果たす土台になるものです。
また、リモートワーク・テレワークを導入することで企業価値(ブランディング)が向上し、求人の応募率も上がることが期待できます。
是非この機会にリモートワーク・テレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか。