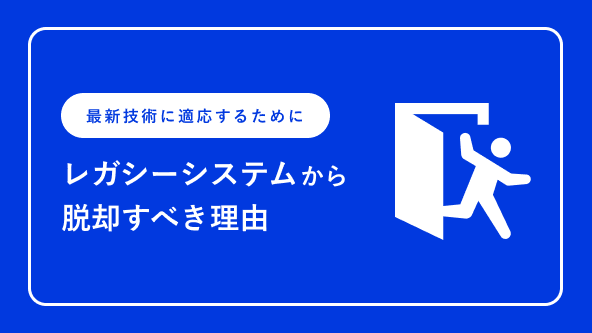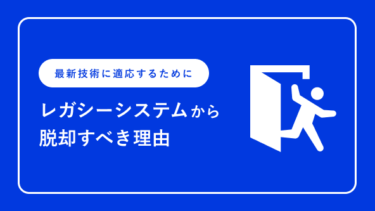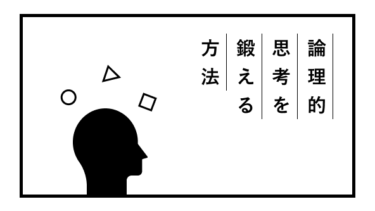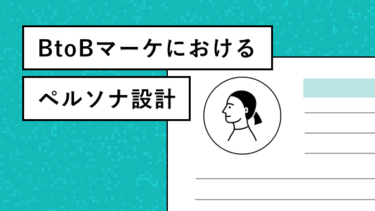今まで日本の多くの企業が活用してきた技術が、ビジネスの環境の変化に対応しきれないということが問題視されています。
また、近年では企業や行政のDX化(デジタルトランスフォーメーション)が推進されていることもあり、レガシーシステムはDX化を阻む大きな課題として関心を集めています。
レガシーシステムはコストの増加、システムの解明ができないことや、IT人材の不足から最新技術の導入が難しいなど、企業や日本の経済にとっても良い影響はありません。
また、DX化では、市場や顧客の変化に合わせた柔軟で迅速な対応をしていく必要があります。
そのため、今後、日本のIT技術の進歩や国際競争力を高めていくためにも、レガシーシステムからの脱却が必要不可欠なのです。
この記事では、
- レガシーシステムとは
- レガシーシステムの問題点
- レガシーシステムからの脱却方法
- レガシーモダナイゼーション
などについて解説していきます。
レガシーシステムとは

レガシーシステムとは、古い技術や仕組みで構築され、複雑化・ブラックボックス化に陥ってしまっている、現代の最新技術に適用できない古びたシステムのことを指すIT用語です。
本来「レガシー(legacy)」とは、「資産」や「代々受け継がれてきたもの」という意味があり、もともとの定義としては、ネガティブな用語として扱われます。
しかし、IT用語での「レガシー(legacy)」は、「古びた時代遅れのシステム」というネガティブな意味になります。
以上のように、古びたシステムを「レガシーシステム」と呼んだりしますが、「どの年代のシステムから『レガシー』と呼ぶのか」といった明確な定義は存在しません。
一般的には、1980年代に多くの企業が導入したと言われている「オフィスコンピューター(※1)」と呼ばれるコンピューターを使ったシステムや、
1990年後半〜2000年代に開発された「オープン系システム(※2)」についても、最新の技術に対応することが難しいため、「レガシーシステム」と呼ばれることがあります。
※1:オフィスコンピューターとは、1960年代〜19990年代頃のコンピューター製品で、企業の事務処理に特化した中型コンピューターのことを指します。
※2:オープン系システムとは、WindowsなどのOS、周辺機器、ソフトウェアなどを自由に組み合わせて構築したシステムです。
レガシーシステムが抱える『2025年の崖』
以前から「レガシーモダナイゼーション」の取り組みはありましたが、2018に経済産業省が発表した「DXレポート」の2025年の崖で更に注目を集めました。
本レポートでは、今後ますますシステムトラブルのリスクは高まり、既存システムの維持管理に高額なコストがかかることを指摘。
予測では2025年〜2030年の間で、年間12兆円(最大値)の経済損失が生じる可能性があると発表しています。
そしてこの難局を2025年に乗り越えられるかどうか?という意味で「2025年の崖」と呼ばれています。
経済産業省『DXレポート』https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
レガシーシステムで発生する問題点

では、レガシーシステムによって、具体的にどのような問題が発生してしまうのでしょうか?
具体的な問題点として、以下の内容が挙げられます。
- 新システムに対応できない
- パフォーマンスが低下する
- レガシーシステムを扱える人材の不足
- クライアントとの取引に支障が生じる
新システムに対応できない
レガシーシステムは新たなシステムとの互換性が低くシステム障害が発生するリスクが高まります。
また、修復や機能の追加などを繰り返し、ブラックボックス化したレガシーシステムでは、データ処理に時間がかかります。
そのため、レガシーシステムによってシステム障害が重症化する傾向があります。
パフォーマンスが低下する
プログラム・ファイルの修正など、度重なるカスタマイズと修正が行われてきたレガシーシステムは、システムのパフォーマンスを著しく低下させます。
その結果、ユーザーがシステムをスムーズに動かせなくなる可能性が出てきます。
レガシーシステムを扱える人材の不足
長年、レガシーシステムの活用を続けている企業では、古いシステム(レガシーシステム)に対応できる技術者が高齢化に伴い毎年退職をしたりと、レガシーシステムを扱える人材の確保が年々難しくなってきています。
常に新しいテクノロジーが生まれ続けている昨今、レガシーシステムについて理解がある技術者の人材確保が今まさに課題となっています。
クライアントとの取引に支障が生じる
システムのアップデートが日々更新される昨今、新しいシステムを導入せずにレガシーシステムを使い続けると、ビジネスの遅延を招く可能性があります。
また、最新のシステムとの互換性が失われ、クライアントなどが離れてしまう危険性もあるため注意が必要です。
レガシーシステムからの脱却における課題
先述したような問題点を解決するためには、レガシーシステムから脱却することが求められます。
しかし、レガシーシステムからの脱却にあたって、以下のような課題もあります。
- 既存のシステム開発をした人材がいない
- コストがかかる
- リスク管理が難しい
既存のシステム開発をした人材がいない
既存のシステム開発を担当した人材が離職や退職をしてしまっている問題があります。
レガシーシステムは、現代から見ると古い技術で構築されています。
古い技術を構築してきた人材が退職や離職すると、その技術のノウハウを知っている人がいなくなってしまいますよね。
また、そういった古い技術は複雑化していることも多いため、システムの解明に時間を要することも。
そうすると、今まで構築したシステムを改修することや、維持することも難しくなってしまいます。
結果的に、最新技術に移行するのに多くの時間と人材が必要になるので、レガシーシステムから脱却できない状態に陥っているのです。
維持管理のコストがかかる
レガシーシステムを改修するためには人材コストがかかってしまいます。
レガシーシステムを一新するためには、ブラックボックス化してしまった構築を解明し、データを移行するなど、多くの工程が必要であるためです。
また、不具合の有無など、綿密な確認をしなければならず、移行後も維持や管理をしていかなければいけません。
そのため、人材にコストをかけるのが難しい企業はレガシーシステムから脱却できない状態になっています。
リスク管理が難しい
レガシーシステムは最新の状態ではなく、設計書がないといったことが少なくありません。
そのため、システム再構築を行う際には、仕様や要件が不明瞭であり、リスク管理が難しくなってしまいます。
リスク管理を十分に行えないと、スケジュールの遅延や、品質問題などの問題点が出てきてしまいます。
レガシーシステムから脱却するには? – レガシーモダナイゼーションについて
レガシーシステムによって起こる問題を解決するために、「レガシーフリー」という手法があります。
例えば、Apple社のMacは「フロッピーディスク」のようなデバイスを排除し、新たなシステムを開発したことから「レガシーフリー」の先駆者と呼ばれています。
一方で、新しい技術で高性能なシステムに一新することはできますが、実際に扱うユーザーに対し、新しいシステムに慣れるまでの手間と時間を負ってもらう必要があるため賛否両論はあります。
そこで最近では、既存のシステムを活かしながら、新しい技術でレガシーシステムを一新する「レガシーモダナイゼーション」という手法が注目を集めています。
レガシーモダナイゼーションの主な手法は以下の通りです。
| 手法 | 意味 |
|---|---|
| リプレイス | 古びた基幹システムを新しいシステムあるいは同等の機能を持つ別のシステムに置き換えること |
| リホスト | 基幹業務で活用される業務システムを「クラウドシステム」などの新システム基盤に移し替えること |
| リライト | 新たなプログラミング言語を用いてソフトウェアを新しい機種やOSに開発し直すこと |
レガシーモダナイゼーションを行う上でのポイント
経済産業省の『DXレポート』を受け、ますますレガシーモダナイゼーションの取り組みが重要視されています。
ここではそんなレガシーモダナイゼーションを行う上でのポイントを解説します。
- 時代に合ったシステムの見直し
- データ移行
- データ連携
ポイント1.時代に合ったシステムの見直し
前述の通り、レガシーモダナイゼーションは
- リプレイス
- リホスト
- リライト
の3つの手法があります。
これらの手法をうまく使って新しい開発言語やツールの機能修復を行い、性能を担保しながら時代に合ったシステムの見直しを行っていきます。
ポイント2.データ移行
システムを一新させることで必要となる作業がデータの移行作業です。
新旧両方のシステムを理解しデータ移行の作業を行う際は、移行すべきデータの確認からはじめます
その後、データ移行用の処理プログラムを開発していきます。
尚、新システムに合わせシステム加工や変換を行う場合には、正しいシステムが作成できているかどうか、突き合わせなどにより確認作業を行う必要があります。
ポイント3.データ連携
積極的にクラウドサービスを活用する企業が増えてきている背景から、レガシーシステムを一新し、システムをクラウドへ移行する企業が増えてきています。
また、SaaSなどのベンダーが提供するソフトウェアを、インターネットを経由して活用する企業も増えつつあります。
このようなクラウドとのデータ連携が必要になってくる理由としては、多様なシステムが自社内に散在した場合に、データ連携を行わず個々のシステムを孤立させてしまうと「サイロ化」に陥る危険性があるからです。
サイロ化とは、システムやアプリケーションが他の事業や部門との連携を持たずに孤立してしまう状態のことを言います。
企業が導入している様々なソフトウェアはサービスによってデータの形式が異なります。そのため、ソフトウェアのフォーマットの違いからデータの連携ができないケースが出てきます。
このような状態が続くと、既存のオンプレミス型(※1)のシステム(レガシーシステム)の保守に関わるコストや人的リソースが増えてしまいます。
そこで、クラウドを活用することで、オンプレミス型のシステム(レガシーシステム)の保守に必要な工数の削減に繋がり、費用に関してもSaaSなどの外部サービスの利用料金のみとなるのです。
今では古びてしまった効率の悪いレガシーシステムから脱却するためにも、クラウドの活用はDX推進を行う上で必須といえます。
※1:「オンプレミス型」と「クラウド型」の違い
オンプレミス型…自社のネットワーク内に専用サーバーがある状態
クラウド型…インターネット上に共有サーバーがある状態
まとめ
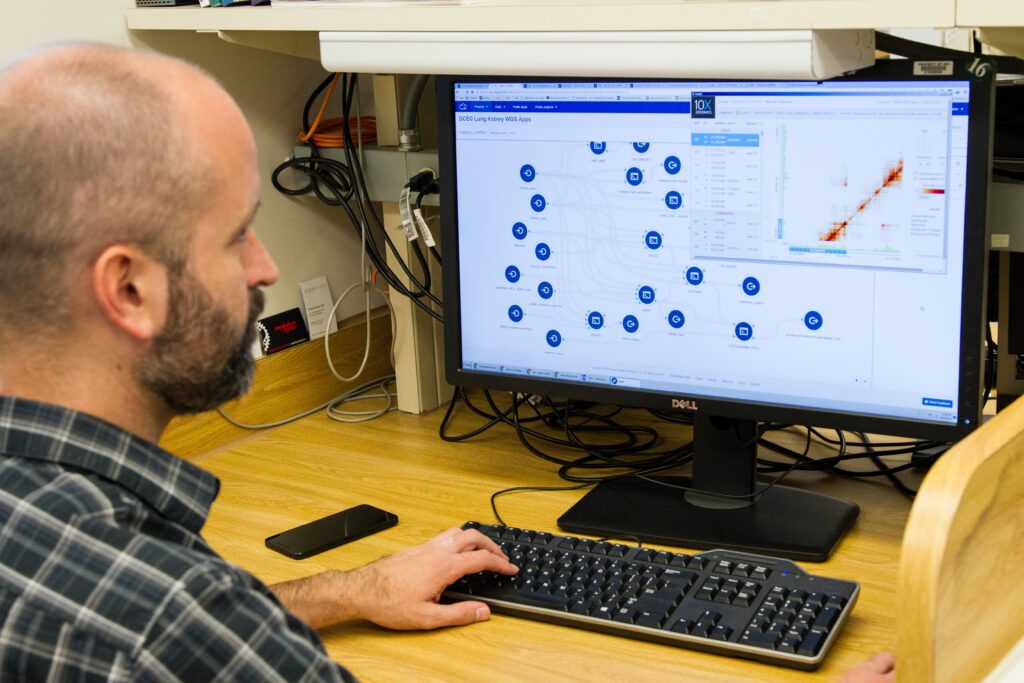
長期にわたり企業で使用されている基幹システムや業務システムの多くがレガシー化しています。
そんな中、経済産業省が発表したDXレポートがきっかけで、対策を始める企業もいれば、既に対策を完了させている企業もあります。
しかし、テクノロジー技術の進化は早く、その度にレガシーモダナイゼーションの取り組みは必要となります。
「2025年の崖」が示す通り、レガシーシステムの一新は企業にとって今後重要な課題です。
テクノロジー技術の進化に合わせて、なるべく早い段階で対策を行う必要があるため、常に情報の感度は高めに設定しておきましょう。