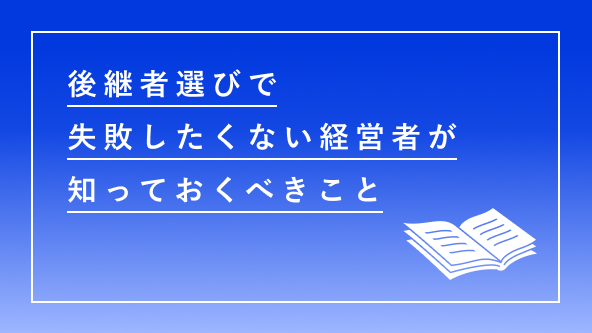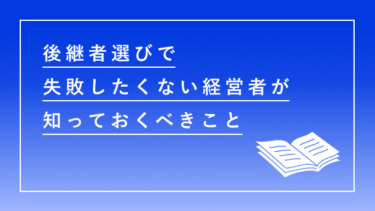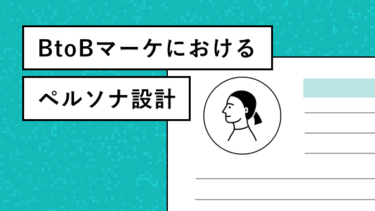近年、中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、「事業承継」は知っておかなければならない知識の一つになりつつあります。
会社を長年続けて経営していくためには、「事業承継」についての正しい知識をつけることは必須と言えるでしょう。
しかし、「事業承継」について具体的に正しい知識を持っている経営者は少ないです。
この記事では、事業承継の概要だけでなく、メリットやデメリット、種類についても詳しく解説していきます。
- 事業承継とは?
- 事業承継の現状と課題
- 事業承継の種類
- 事業承継を成功させるためのポイント
- 事業承継の相談先
事業承継とは

事業承継は、現在の経営者が後継者を探し、自社または事業を引き渡すことをいいます。
事業そのものだけでなく、 会社であれば株式やその他の財産、役員などの、事業に関する全てのものを引き継ぐことになり、引き継がれたものは全て譲渡と見なされます。
その一方で、 元の経営者が亡くなり、後継者が事業承継をする場合には、承継されたもの全てが財産と見なされるため、相続税の課税対象となります。
事業承継の現状と課題
現在、事業承継は大きな課題となっています。
特に、中小企業では事業承継の問題が深刻化しつつあるのです。
なぜ中小企業で深刻化しているのかというと、中小企業の平均年齢が過去20年間で19歳と、上昇傾向にあるためです。
この事から、若い世代への経営交代がうまくいっていないことが分かるでしょう。
さらに、廃業を予定している中小企業のうちの29%が廃業予定理由に後継者難をあげています。
中小企業省が作成した「事業承継ガイドライン」では、『中小企業の平均引退年齢は70歳である』と言われています。
事業承継を行うにあたって、後継者の育成も含めると5年〜10年の準備期間を要します。
つまり、中小企業の経営者の平均年齢を考慮すると、多くの企業で事業承継までのタイムリミットが迫ってきているといえます。
そのため、事業承継を考えている経営者には早急でスムーズに対応していくことが求められています。
事業承継の種類と注意点

事業承継には、
- 親族内承継
- 親族外承継
- M&A
の三つの種類があります。
それぞれの事業承継を行う際のメリットとデメリット、注意点を紹介していきます。
親族内承継(子息などに承継する)
親族内承継は、経営者の子供や親族に承継していくことを指します。
特に中小企業で主に行われており、日本において最も一般的と言われる親族内承継です。
しかし、現在は親族への事業承継は40%程度で、以前よりも減少傾向にあるのが実態です。
親族内承継のメリット
- 従業員や取引先など、社内外のステークホルダーに受け入れられやすい
- 後継者に、株式や専業用資産などを、相続などによって引き継ぐことができる
先ほど述べた通り、日本において最も一般的な承継方法ですので、トラブルを起こすことなく承継できる割合が高いです。
もし後継者候補の方に経営を引き継ぐ気持ちがあるのであれば、早いうちに社内外に知らせておくべきでしょう。
そうすることで、早い段階で周囲が次の後継者を認識し、後継者は信頼を得ることができます。
また、日本では高齢化のために事業承継が国全体の課題とされています。
そのため、事業承継が進めやすくなるような税制措置があります。
例えば、上場していない中小企業が株式の承継を行う場合は、ある条件を満たせば贈与税・相続税納付の猶予や免除が可能となります。
もし親族内で事業承継をするのであれば、こういった税制措置を活用することができるでしょう。
親族内承継のデメリット
- 後継者の教育に時間がかかる恐れがある
- 後継者と後継者ではない親族との間で、相続の問題が起きやすい
後継者が別の会社に所属していた場合、引き継いだ会社との文化の不一致により、元々働いていた従業員との間に齟齬が生じる可能性があります。
そうなってしまうと、従業員や重要な人材が退職してしまう、モチベーションの低下など、経営に悪い影響を及ぼしてしまうでしょう。
そのために、後継者の教育に時間をかけ、自社に馴染ませていくことや、従業員に周知させることが必要です。
事業承継をするにあたって、相応の時間が必要であることは認識しておきましょう。
また、家族から反対されるケースもあります。
経営者は、事業資金を借り入れる場合、家族が保証人になる必要がある場合があるためです。
そのように、後継者の家族が、責任を負わなければいけないということに関して慎重になることも少なくありません。
こういったケースを避けるためには、後継者だけではなく、後継者の家族とも良い人間関係を普段から築くことが重要です。
親族外承継(自社役員、社員に承継する)
親族外承継は、親族以外の人を後継者とする方法です。
大企業では、外部の人物が後継者となることも多くありますが、中小企業の場合は、親族以外となると、必然的に従業員のことを指します。
親族外承継のメリット
- 多くは、従業員だった人が後継者になるため、実際に仕事を見て業務を任せられるか、見極めることができる
- 従業員とも取引先とも、既に付き合いがあるため、交遊関係を新たに築くことなく引き継ぐことができる
親族外承継は、親族内承継よりも後継者候補の幅が広がることがメリットと言えるでしょう。
従業員を後継者とするのであれば、会社の後継者に適合する、素質のある人材を見つけることができます。
つまり、会社の維持や向上を一番に考えて後継者を選ぶことができるのです。
また、元々、他の従業員や取引先と既に関わりがあるため、周囲に認知させるという負担が減ります。
会社の文化の齟齬などもないので、教育にかける時間も、他の承継方法よりは少なくなる可能性があります。
親族外承継のデメリット
- 後継者が株式や専業用資産などを買い取る場合にまとまった資金が必要となる
- 後継者が資金力がない場合がある
後継者に対して株式譲渡も行うのであれば、後継者自身が株式や専業用資産を買い取るための資金を用意しなければならない場合があります。
もし、後継者本人が資本家で、資金力があるのなら特に問題ありません。
しかし、MBOによる親族外承継を行うのであれば、後継者に十分な資力がないというケースもあります。
その際には、融資などで対応できるのかなど、事前準備を十分に行なっておきましょう。
M&A(第三者企業に承継する)
M&Aは、企業の合併や買収のことを指す言葉です。
M&Aを実施することができると、会社を売り、事業を引き継いで貰うことが可能になります。
簡単にいうと「会社を売る」ということです。
日本では社外の第三者に会社を売ることに抵抗がある方が多く、後継者が見つからなかった場合に廃業を選ぶ経営者も多いようです。
しかし、M&Aによる事業承継は日本経済にも利益をもたらす手法であるため、中小企業庁はM&Aを使った事業承継を勧めています。
そのためか、中小企業がM&Aを活用して事業承継を行うケースは年々増えている傾向にあります。
M&Aのメリット
- 条件の合理を得ることができればすぐに事業承継することができる
- 売却先の経営力が高ければ事業をさらに発展させることが可能になる
- もとの経営者に会社の売却代金が入る
M&Aでの事業承継は、他の手法よりも手続きが簡単です。
売り手が中小企業の場合、売り手と買い手お互いの同意のみでM&Aを行うことができるためです。
もし、売り手企業が株式に譲渡制限をかけているという場合は、売り手の株式総会や取締役会で譲渡を承認するための手続きを行わなければなりません。
しかし、この時手続きを含めても、多くの会社は株主が少数のため、他の手法よりは簡単です。
M&Aのデメリット
- 業績の好調などの魅力がないと購入を希望する企業が現れにくい
- 売却後はもとの従業員の雇用や待遇が保証されない恐れがある
M&Aについてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひあわせてお読みください。
新規事業の立ち上げを自社で一から立ち上げるには膨大な経営資源と時間が必要となってきます。 ビジネスのスピードは年々加速しており、新規事業を立ち上げる間に市場が変わってしまう可能性があります。そこで注目されているのがM&Aによ[…]
事業承継の相談先

事業承継を考えている方の中には、自分だけでは手が回らないかもしれない、と心配している方もいるかと思います。
ここからは、事業承継の相談先について紹介していきます。
- 税理士
- 弁護士
- M&A専門のコンサルティング会社
- 事業引継支援センター
税理士
事業承継には、税務会計の知識は必須です。
特に顧問税理士は、その会社の内情や財政状況について熟知しているので、強い味方になります。
税理士によっては、M&Aの仲介まで行える場合もあります。
しかしながら、知識不足によって事業承継を満足に取り扱えない税理士も、もちろんいます。
仮に、顧問税理士に事業承継を相談できない場合には、事業承継に長けている税理士の紹介を受けるとよいでしょう。
もちろん独自に探すことも可能ですが、顧問税理士とつながっている税理士の方が、互いに連絡がとりやすいというメリットがあります。
弁護士
事業承継やM&Aを専門とする弁護士に相談すると、相続やM&Aで訴訟や法律問題が生じた際に、手厚いサポートを受けることができます。
M&A専門のコンサルティング会社
M&A専門のコンサルティング会社は、M&Aの相談や仲介を専門にしている一般企業です。
M&Aに特化しているので、豊富な知識と経験でサポートすることができると同時に、購入を希望している企業の中で、もっとも適した承継先を紹介を受けることができます。
加えて、必要に応じて提携先の税理士や弁護士などの専門家や、在籍している専門家に相談することもできるので、M&Aにたいして万全な体制をとっているといえます。
ただし、「法外な報酬の請求」や「無理やりM&A契約を提携させる」といったことを行う悪徳業者も少なからずいるため、注意しなければいけません。
事業引継支援センター
事業引継支援センターは、国が中小企業の事業承継をサポートすることを目的として、設置した公的機関です。
47都道府県に設置されていて、事業承継に関する相談や情報提供、マッチング支援を主に行っています。
また、公的機関なので、相談料は無料でもちろん営業をかけられる心配もありません。
気軽に相談できるので「まず、事業承継とは何か、どうしたらよいのかなどの基本的なことを聞いてみたい」という時に、利用してみたらいかがでしょうか。
事業承継を成功させるためのポイント
事業承継をトラブルなく成功させるためには、次の3つのポイントに気を付ける必要があります。
- できるだけ早くから計画すること
- 後継者を教育しておくこと
- 税金対策をしておくこと
- 相続トラブル対策をしておくこと
詳しく解説していきます。
できるだけ早くから計画すること
事業承継は、時間がかかる行為です。
親族や自社の従業員を、後継者にしたい場合、早い段階で教育していく必要性があります。
加えて、後継者が会社の株式を買い取る場合には、資金調達をする時間も必要になります。
M&Aは、短時間で行うことができるというメリットを持ちますが、条件にあう売却先がすぐに見つかるとも限らないので、早めに相談し始めることが最善策といえます。
後継者を教育しておくこと
事業承継を行う上で、後継者の教育は必要不可欠です。
事業承継をするということは、会社のトップになるということです。
会社のトップは、サラリーマンの感覚とは異なり、 経営の基礎から教育していく必要があります。
特に、親族への承継となると、元々全く別の分野の仕事をしていたというケースもあり、その場合、新入社員への教育と同じようなものになるので、さらに時間が必要になります。
税金対策をしておくこと
事業承継において、後継者に引き継がれるものは、株式などの様々な財産となります。
引き継がれた株式などの財産には、贈与税や相続税といった税金がかかります。
また、後継者だけでなく、先代経営者に対しても所得税が発生します。
例えば「現金を100万円渡した」という場合には、税率が比例して多くなっていきます。
しかしながら、あまりにも大きな税金を課してしまうと、事業承継がうまく行われなくなってしまいます。
そのため、国は、事業承継にかかってしまう贈与税や相続税においては、納税の猶予期間を設けています。
事業承継でかかる税金の節税は、節税方法を知っていることと、事前にシミュレーションすることが大変重要なポイントです。
相続トラブル対策をしておくこと
親族を後継者にする際に起こるのが、遺産分割のトラブルです。
経営者の遺産の大半が、会社関連のものだと、遺産のほとんどを後継者が相続することになり、不公平が生じてしまうため、相続トラブルが起きてしまいます。
事業用財産を、後継者以外が相続し、それを会社側が借りるという方法もとれますが、経営に支障が出てしまう可能性があります。
相続によって事業承継をする場合には、あらかじめ遺言状を作成しておくことをオススメします。
まとめ

ここまで、事業承継の種類と注意点、準備するべきことを紹介してきました。
後継者に、事業を引き継ぎたいという経営者の方は、誰に引き継ぐのか、引き継ぐにあたって準備できているかを確認する必要があります。
専門家への相談や後継者の教育、M&Aを行う場合は、売却先の決定など数多くのやるべきことがあります。