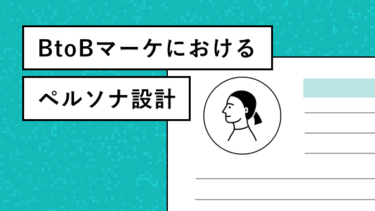商品やサービスのブランディングやマーケティング戦略を考える上で「ターゲティング」は重要な指標の1つと言われています。
なぜなら、狙ったターゲットに自社の製品やサービスが届かなければ、商品が売れないからです。
つまり、マーケティングを行う上で、ターゲティングを行なっていないと、ビジネスやマーケティング戦略が失敗してしまうかもしれないのです。
ターゲティングはマーケティング戦略を考えていく上で重要な指標となるため、経営者の方やマーケティング担当者の方はしっかりおさえておくべきです。
そこで今回は、
- ターゲティングとは
- ターゲティングの重要性
- ターゲティングのフレームワーク
- ターゲティングの成功事例
について解説させて頂きます。
ターゲティングとは

ターゲティングとは、STP分析の一つで、市場分析を行い、自社の商品やサービスを購入して欲しい客層(ターゲット)を絞り込むマーケティング戦略を指します。
一言で「お客様」といっても世の中には様々な年代、職業、ライフスタイル、家族構成の人がいるなかで、全員が自社の製品やサービスを購入してくれるとは限りません。
そこで、まずは業界の市場をグループ分けします。
その中で、顧客からのニーズがあり、尚且つ、自社の製品やサービスとマッチする市場にターゲットを定める行為がターゲティング戦略となります。
グループ分けの方法としては、世代別、職業別、地域別、年収別など複数存在しますが、これらを掛け合わせて自社の製品にマッチする市場を定めるのも効果的です。
ターゲティングに従ってマーケティング戦略を立てていくため、なるべく早い段階で正確に行う必要があります。
STP分析でのターゲティング
ターゲティングは、マーケティング戦略でよく使われているSTP分析というフレームワークの一つです。
STP分析は、
| セグメンテーション(Segmentation) | 市場を特定の要因や条件で細分化する |
| ターゲティング(Targeting) | 自社の商品やサービスを売り込む市場を選定する |
| ポジショニング(Positioning) | 市場における自社独自の魅力を作る |
の3つのフローがあります。
セグメンテーション
セグメンテーションは、「市場の細分化」を表します。
市場と一概に言っても、その中にいる顧客の年齢、性別、居住地、嗜好などはバラバラです。
一つの軸を決めて、その軸を基準に市場を細分化していくことで、市場の状態を理解することができます。
例えば、
- 居住地や気候などの地理的要因
- 年齢や性別などの人口統計学的要因
- 趣味嗜好や関心のある出来事などの心理的要因
などの軸を基準に細分化します。
そして、細分化された顧客をさらに分析・調査していくのです。
セグメンテーションは、ターゲティングのための準備とも言えるでしょう。
ターゲティング
ターゲティングは、「市場の選定」を指します。
セグメンテーションで細かく分けた市場の中で、自社の強みを活かして売り込んでいけそうな顧客を決めていきます。
自社の商品・サービスを売り込む顧客を絞っていくことで、より効果的で具体的なマーケティング戦略を考えることができ、顧客のニーズを満たすことにも繋がります。
逆に、ターゲティングが行われていないと、ターゲットの幅が広くなってしまうため、商品・サービス自体のコンセプトや戦略がはっきりとせず、マーケティングが失敗に終わってしまうかもしれません。
また、闇雲にマーケティング戦略を行ってしまうと、時間やコストの無駄にもなってしまいます。
そのため、ターゲティングでは、「どんな人が自社の商品・サービスを欲しいと思うか」ということを考えなければなりません。
ポジショニング
ポジショニングは「自社の位置を決めること」を指します。
ポジショニングでは、同じ市場にいる競合他社がどんな強みを持っているのか分析し、「自社が持つそんな独自の強みを活かしていくか」ということを考えます。
似たような商品・サービスはあっても、価格や操作性、クオリティなど、必ず違いがあるはずです。
その中のどんな差異を自社商品・サービスにしかない魅力として売り出していくか、ということを考えるのです。
例えば、大手カフェチェーンのスタバ。
他にも数多くのカフェチェーンがある中で、スタバは他のカフェより少し価格が高いですが、それでも人気を得ています。
それは、スタバが「都市部で平均以上の収入を得ているオフィスワーカー」というターゲットに対して「都市部のおしゃれで少し高めのカフェ」という存在として確立しているためです。
このように、STP分析を行い、市場を理解し、ターゲットを定めることで、マーケティング戦略は成功に近づきます。
デザイン新聞では、他にもさまざまな分析方法のテンプレートや、ダウンロード資料を配布しています。
新規事業をお考えの経営者の方やマーケティングの担当者の方はぜひご活用ください!
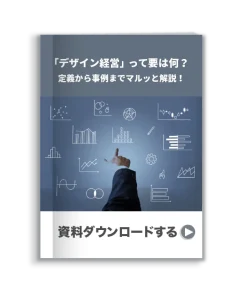
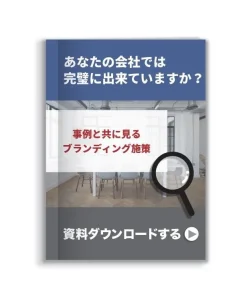
ターゲティングの重要性
自社の事業やビジネスを成功させるためには、まずはターゲティングが重要であると言えます。
なぜなら、自社の製品やサービスが狙った客層(ターゲット)にアプローチできていなければ、そもそも商品が売れないからです。
つまり、最初の段階でターゲティングを適切に行わないと、そこから派生する戦略やビジネスは失敗に終わる可能性があります。
そのため、自社の事業を成功に導くためにも、まずはターゲティングを適切に行う必要があるのです。
6R|ターゲティングのフレームワーク

では、具体的にどのような流れでターゲティングを行うのが良いのでしょうか。
ここでは「6R」と呼ばれるフレームワークに沿って解説していきます。
6Rとは、ターゲティングを行う際に活用する6つの指標のことを指します。
具体的には以下の指標です。
- 有効な規模(Realistic scale)
- 優先順位(Rank)
- 成長率(Rate of growth)
- 競合(Rival)
- 到達可能性(Reach)
- 測定可能性(Responce)
上記6つの頭文字をとって「6R」と言われています。
6Rを活用してターゲティングを行う際は、それぞれの指標に偏りすぎず、6つの指標について総合的に見ていくことが重要です。
それでは具体的に解説を行っていきます。
1.Realistic scale:市場規模は適切か
まず最初の指標は、マーケットの規模を示す指標です。
狙っているのが大きな市場の場合、多くの利益をもたらす可能性も大きいため、戦略的にもマーケットは大きい方が良いとされています。
ただその一方で、市場が大きい場合はマーケットの成長率やライバル数などを把握しておく必要があります。
たとえば、今現在大きな市場であったとしても、時代の変化に対応しきれず衰退したという事例もあるため、単純に大きな市場だけを狙うということは望ましくありません。
逆に、市場は小さいものの一定の客層をターゲットにし、安定したサービス提供を行うという考え方も存在します。
「ニッチ産業」とも言われますが、ターゲットを絞り込むことで競合の参入を避け、安定した収益確保につなげることが可能です。
2.Rank(優先順位):ユーザーの優先度
2つ目の指標は、ユーザーの優先度を判断する指標です。
ターゲット層の興味・関心が高い商品やサービスを提供することで認知度を上げることができます。
加えてメディアやSNSなどで拡散されることで一気にターゲット層に自社製品のPRを行うことも可能です。
つまり、「メディアやSNSなどで拡散されやすい仕組みが十分に整えられているか」といった指標もターゲティングを行う上で重要な要素と言えるのです。
3.Rate of growth(成長率):成長が期待できる市場かどうか
3つ目は、市場の成長が期待できるかどうかを示す指標です。
自社の競合の売上や対象となるカテゴリの商品、サービスの相場などを参考に判断していきます。
Realistic scale(市場規模)やRival(競合)と併せて比較することで、市場の全体像を把握することもできます。
例えば、市場が成長段階なら売上が伸びることも期待できますし、技術革新や市場の変化に伴って、新たな需要が生まれるケースもあります。
その反面、すでに成熟している市場では今後衰退してしまう可能性もあるため、避ける方が無難です。
可能な限り、将来的な成長を見込める市場を選びましょう。
4.Rival(競合):競争把握
4つ目は、他社競合の商品やサービスの規模を把握する指標となります。
市場は基本的に競合がいない「ブルーオーシャン」が理想です。
未開拓の市場ほど競合との差別化を図ることなく参入することができ、大きな市場を獲得することができます。
しかし、この指標だけで判断してしまうとビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあるため注意が必要です。
例えば、競合の数は多いけど市場規模が大きければ、まだ新規参入が間に合う場合もあります。
また、強い大手企業がいる場合でも、大手企業が参入できないポジションもあります。
そのため、競合数だけでなく、6Rの他の指標と併せて見極めることがポイントです。
5.Reach(到達可能性):的確にターゲットにアプローチできているか
5つ目は、的確にターゲットにアプローチできるかを判断する指標です。
企業が様々な広告やプロモーションを行なっても、ターゲットに届かなければ意味がありません。
例えば10代の若者向けのサービスを提供しているとします。そこで、広告として
「Facebook広告」を行なっても集客は難しいです。
なぜなら、Facebookの利用者層は30代、40代がメインだからです。
つまり、狙ったターゲット層が、「よく利用するSNSは何か?」「よく集まるメディアはどこか?」といった視点でアプローチすることが重要となります。
この指標は意外にずれてしまう傾向にあるため、しっかりターゲットにリーチできる場所を明確にしておきましょう。
6.Response(測定可能性):ターゲットからの反響を測定できているか
6つ目は、ターゲットからの反響を測定できているかを判断する指標です。
実際に、ターゲットにアプローチして、どれだけの反響があったかを測定し、「数値化」していくということはとても大切なことです。
例えば、広告を出稿することで、ユーザーの流入数や反響率、その先の商談数や受注率など、数値化を行うことによって、次のマーケティング戦略の打ち手を考えることもできます。
また、具体的な数値を行うことで、組織のモチベーションやメンバー評価を行うこともできるため、数値の測定は積極的に行なっていきましょう。
ターゲティングの成功事例
最後に、ターゲティングを行うことで成功した企業の成功事例をご紹介します。
事例1.無印良品
素材やデザインのシンプルさが人気の無印良品は「派手な商品よりシンプルな商品を利用したい」という客層をターゲットにすることで、「シンプルな雑貨・家具を購入するなら無印良品」という認識を消費者に持たせることに成功しています。
また、創業当初からの「シンプルな商品を提供していく」という理念を崩すことなく経営を継続しており、今となっては後発企業の参入が難しい状況を作り出しています。
結果として、ターゲットの絞り込みと市場でのポジショニングを見事に獲得している成功事例と言えます。
事例2.スタジオアリス
スタジオアリスは、今となっては規模の大きい「フォトスタジオ」というイメージですが、元々は家族写真を撮ることができる「町の写真屋さん」というイメージでした。
そこで、従来のイメージを払拭し、「子どもの写真をいつまでも綺麗な状態で残しておきたい」「子どもと一緒に綺麗な家族写真を撮りたい」という新たな価値観を訴求することで、新たな客層(ターゲット)にアプローチすることができ、競合がいない市場でシェアを拡大することに成功しました。
結果として、「子どもや孫と一緒に写真を撮りたいという」という親や祖父母をターゲットとした成功事例となりました。
まとめ

今回はターゲティングの意味や重要性、ターゲティングを行う流れについて解説しました。
商品やサービスのターゲティングを検討する際、自社の思うがままに市場分析を行っても良い成果は見込めません。
また、企業がイメージする「理想の客層(ターゲット)」と、実際に商品を購入してくれた客層にズレが生じているというケースはよくあります。
そうなってしまうと、その後のリピーター獲得や新規顧客獲得のための戦略立てでも苦しむことになります。
ターゲットを明確にし、ターゲットに適切なマーケティング戦略を行うことで、効率的にマーケティングを行うことができるのです。
新規事業を考えている方や、自社商品・サービスの伸びが見られずお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。