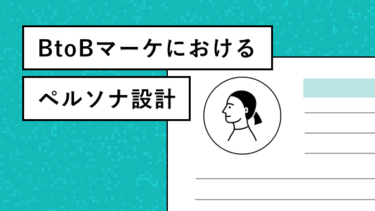「のれん償却」という言葉をご存じでしょうか?
「のれん償却」とは、買取された企業の時価評価純資産と実際の買収価格の差額である「のれん」を減価償却することを指します。
「のれん償却」をニュースなどで聞いたことがあっても意味をよく理解できていないという方のために、今回はのれん償却の意味や、メリット・デメリットについても解説していきます。
のれん償却の「のれん」とは?

ビジネス業界において、主にM&Aが行われる際に発生することが多い「のれん」は、買収された企業の時価評価純資産と、実際の買収価格の差額のことを指します。
M&Aが行われる際、買収元の企業は買収先の企業の収益力の高さや、営業権やノウハウなどを評価して買収するため、基本的には買収先の企業の正式な価値(純資産額)よりも高い価格で企業を買います。
つまり、「のれん」は買収先の企業における「ブランド的価値」と言えるでしょう。
しかし、賃借対照表には現金や土地などの有形固定資産は記載されていますが、のれんは無形固定資産であり、決まった価値というものがないため、賃借対照表には記載されていません。
したがって、M&Aの際は買収元の判断に基づいて「のれん代」が決まり、買収価格に上乗せされることになります。
のれん償却とは?

のれん償却とは、「のれん」を「減価償却」することを指します。
M&Aにおいて計上するのれんも、特許権やソフトウェアのような無形固定資産と同じように、減価償却して費用を計上する必要があります。
のれんは基本的に価値が減少せず、むしろ使用することによって利益を増やしたり、シナジー効果を獲得することが可能になります。
そのため、のれんが持っている付加価値は使用することによって会社にとって利益をもたらすことができ、のれん償却は利益獲得のために獲得した付加価値を表すための処理だということができるのです。
のれんの償却方法と償却期間
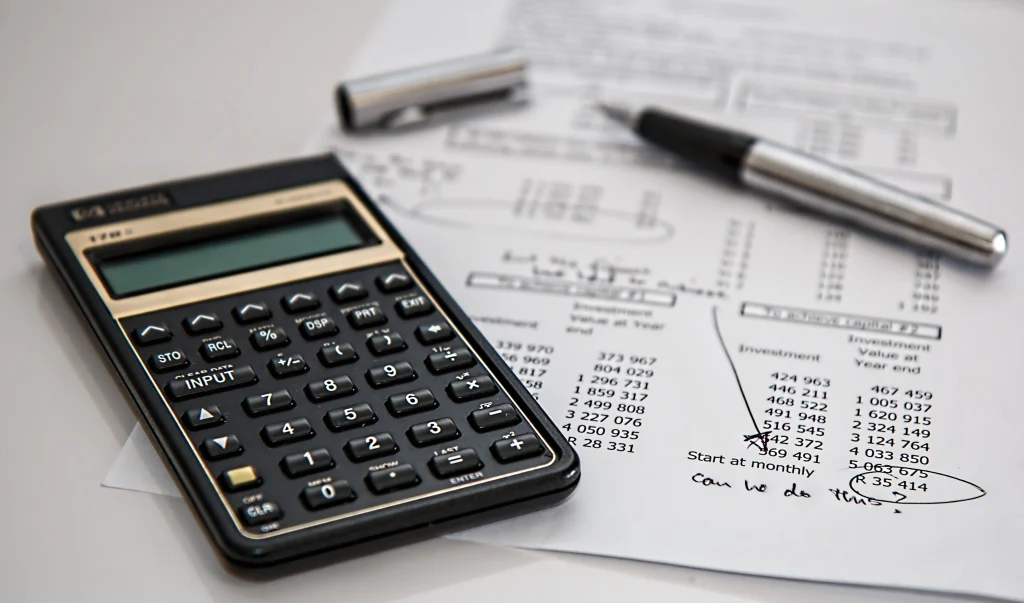
ここからは、のれんの償却方法について解説していきます。
前述したとおり、のれんは無形固定資産であるため、基本的には特許権やソフトウェアの償却と同じように、定額法を用いて償却していくことになります。
例えば、資産800,0000円、負債200,0000の会社を100,00000円で買収した場合、のれんは以下のようになります。
資産800,0000円、負債200,0000の会社を100,00000円で買収した場合の例
のれん = 100,00000 – (800,0000 – 200,0000) = 400,0000円
上記の例では、400,0000円を資産として計上することになり、資産計上したのれんは一定期間内に減価償却を完了される必要があるので注意しましょう。
上記の例を10年間でのれん償却させる場合は、以下のようになります。
のれん償却費 = 400,0000 ÷ 10(年) = 400,000円
この場合、10年間にわたって毎期400,000万円を計上しなければいけません。
また、のれん償却には20年以内に終わらせなければいけないというルールがありますので注意が必要です。
のれん償却のメリット・デメリット
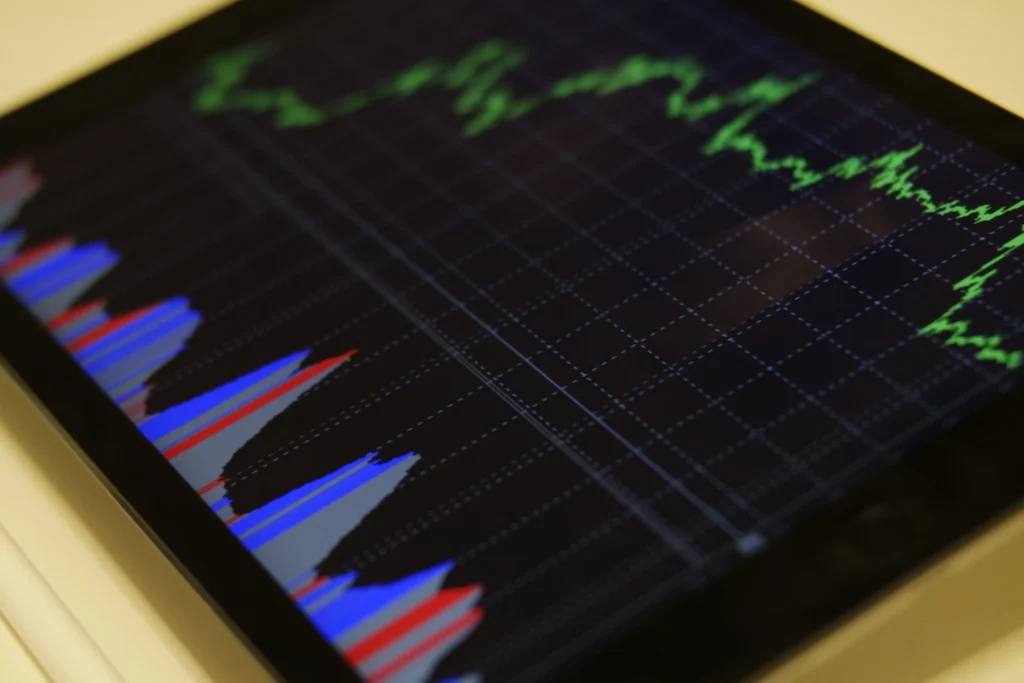
ここからは、のれん償却のメリット・デメリットをこちらで説明していきます。
ただし、日本企業であればのれん償却は必ず行う必要がありますので、メリット・デメリットで表すことはできません。
しかし、日本の会計基準では、のれん償却が採用される一方で、国際財務報告基準(IFRS)ではのれん非償却を採用するルールが適用されます。
大規模なM&Aが行われる場合、日本企業であっても会計ルールを日本会計基準から国際財務報告基準に変更するケースもあり、のれん償却を行わないという事例も増えています。
まずは、のれん償却のメリットについて解説します。
のれん償却のメリット
のれん償却のメリットの一つは、のれんの非永続性を反映し、損失時の影響を抑える事ができることです。
のれんには、価値が永続しないという特徴があり、時には価値が大きく低下するケースもあります。
そのため、M&Aの際に生じたのれんを売却していない状態でのれんの価値が著しく低下した場合、多額の損失を計上しなければなりません。
予定していた予算の損益から外れることを防ぐためにも、のれん償却を行い、非永続性を決算に反映させるようにしましょう。
のれん償却のデメリット
- のれん償却期間中は営業利益が圧迫されやすい
- のれん償却の負担がかかる
のれん償却のデメリットは、のれん償却期間中は利益が圧迫されやすいという点です。
一定期間内であれば、のれんの償却期間は任意に設定することができますが、最長でも20年間は利益が圧迫されることになります。
一方で、償却期間を短く設定することも可能ですが、償却期間を短くしたことで毎期の利益への影響も大きくなることになります。
M&Aを行う際、売り手はできるだけ高い価値で売却したいと考えますが、買い手は利益への圧迫を少しでも抑えようとするため、可能な限りのれんは小さくしたいと考えるでしょう。
したがって、のれんが大きすぎることは、買い手がM&A自体に対して消極的になることの原因となります。
のれん非償却のメリット・デメリット

次にのれん非償却のメリット・デメリットについて解説します。
のれん非償却のメリット
- のれん償却の負担がない
- 営業利益が圧迫されない
のれん非償却のメリットは、のれん償却の負担がないことです。
のれん償却の費用は「販売費及び一般管理費」として計上されるため、営業利益の圧迫に繋がります。
企業を買収したあとも、その企業が落ちることなく順調に利益を上げることができるのであれば問題ありませんが、のれん償却費が利益を上回ってしまった場合、営業利益や利益率が悪化することになります。
それらを懸念して、M&Aをためらう企業もいます。
一方で、IFRSを採用した場合はのれん償却をする必要がないため、積極的にM&Aを行うことができるでしょう。
大規模なM&Aを行う際に日本企業の多くがIFRSへ移行している理由は、IFRSへ移行することでのれん償却をしなくても良いというメリットがあるからです。
しかしながら、IFRSに移行していたとしても、買収した企業が予定していたよりも利益をあげられなかった場合は、通常通り減損処理をしなければならないので注意が必要です。
のれん非償却のデメリット
- 減損処理が発生した場合の損失が大きい
- のれんの価値が過大評価されたまま計上される
のれん非償却のデメリットは、減損処理が発生した場合の損失が非常に大きいことです。
のれん非償却の場合は毎期にのれん償却を行っていないため、利益に与える損失は一層大きくなります。
また、のれん償却を行わないことで、のれんの価値が過大評価されたまま計上されることになるという意見や、減損処理はのれんの価値をタイムリーに判断できるのかという批判もあります。
加えて、減損テストを行うことは多額のコストが必要になるため、のれん償却をしたほうが手続き面と費用面でメリットが大きいという意見もあります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
のれん償却の期間は最長でも20年に設定することが可能ですが、そうすると20年間利益を圧迫することになります。
毎期に発生する負担を軽くして期間を長くするのか、毎期の負担は大きくなるけれど期間を短くするのかといった判断は慎重に行いましょう。
売り手側も、のれん償却に関しての正しい知識を身につけて、買い手側がM&Aに対して消極的にならないように考慮する必要があります。
また、IFRSを導入してのれん償却を実行しないということも選択肢のひとつとして考えておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。